相続登記にかかる登録免許税とは?免税措置/計算方法/納付まで徹底解説
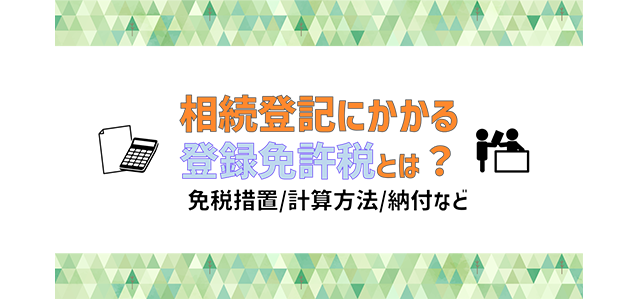
この記事の目次
1.相続登記にかかる登録免許税とは
登録免許税とは、登録免許税法に基づき、登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定及び技能証明について課せられる国税です。
相続登記を含む不動産の所有権移転登記にも、登録免許税法を根拠に登録免許税が課せられます。登録免許税法には、課税標準額及び税率が定められています。
不動産の所有権移転登記にかかる登録免許税の課税標準額は、不動産の価額と定められています。
不動産の所有権移転登記にかかる登録免許税の税率は、2通りの税率が定められています。
税率:0.4%
2. その他の原因による移転の登記*
税率:2%
※その他の原因による移転登記とは、不動産の売買や贈与等を原因とする移転登記のことをいいます。
相続登記にかかる登録免許税は、登記の時点における不動産の価格に0.4%の税率をかけて計算します。登録免許税を納付しなければ、登記申請は却下されます。また登録免許税の額を誤って納付すると、別途、不足しているならその不足を補う手続き、過納付しているなら還付を受ける手続が必要となる場合があります。
この記事では、相続登記にかかる登録免許税の計算方法や免税措置、納付方法などについて詳しく解説します。
2.相続登記にかかる登録免許税の計算方法
ここでは、相続登記にかかる登録免許税の計算方法について解説します。
2-1.相続登記の登録免許税の計算式
相続登記にかかる登録免許税の計算式は、以下のようになります。
登録免許税を計算する際の不動産の価額とは、固定資産税評価額です。不動産が数筆ある場合は、全ての不動産の価額を合計します。そして、合計して得られた額のうち、1,000円未満の端数を切り捨てます。切り捨てた後の額が課税標準額になります。
次に、課税標準額に税率(0.4%)を掛けます。税率を掛けた後の額に100円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てます。
以上の計算によって得られた額が、登録免許税の額となります。
課税標準額に税率を掛けて得られた額が1,000円未満の場合、登録免許税は1,000円となります。数筆ある不動産の相続登記を一度に申請する場合において、上記のとおり計算して得られた額が1,000円未満になった場合も、登録免許税は同様に1,000円となります。
2-1-1.固定資産税評価額を調べる方法
固定資産税評価額は「固定資産税・都市計画税 課税明細書」、または「固定資産評価証明書」などで調べることができます。
では、いつの固定資産税評価額を適用するかといいますと、登記を申請する日が属する年度(4月1日~翌年3月31日まで)の固定資産税評価額が適用されます。年度が変わる3月末から4月上旬に申請される場合は特に注意が必要です。
例えば、令和2年12月15日に登記申請をするのであれば、令和2年度の固定資産税評価額が基準となります。また、「年」ではなく「年度」とありますので、登録免許税の計算は、令和3年3月31日に登記申請をするのであれば令和2年度の固定資産税評価額が適用されます。令和3年4月1日に登記申請をするのであれば令和3年度の固定資産税評価額が適用されます。
固定資産税評価額は、毎年4月から5月頃に自治体から送られてくる固定資産税の納税通知書に同封されている「固定資産税・都市計画税 課税明細書」にも記載されています(名称は自治体によって若干異なります)。
「課税明細書」には、「価格」もしくは「評価額」という欄があります。「価格」もしくは「評価額」に記載されている額が、所有している不動産の評価額になります。「固定資産税課税標準額」ではありませんので、注意してください。
※所有している不動産が複数であれば、不動産毎に記載されています。
「課税明細書」が手元にない場合は、役所等で「固定資産評価証明書」を取得して確認することができます。
固定資産評価証明書は、固定資産課税台帳に登録された様々な事項を証明する書類です。固定資産評価証明書を取得できるのは、原則としてその情報に記されている固定資産を所有している人物、あるいはそれに準ずる人物に限られます。無関係な人は取得することができません。
固定資産評価証明書の発行手数料は1物件あたり300円程度です(自治体により異なります)。
固定資産評価証明書を取得できる窓口は、お住まいの地域によって異なります。市区町村が指定する役所や出張所、自治体によってはコンビニエンスストアでも取得することができます。
窓口や必要書類は自治体によって異なりますので、各自治体にご確認ください。
2-2.相続登記の登録免許税の計算シミュレーション
次に、登録免許税の具体的な計算方法について解説いたします。
2-2-1.登録免許税の計算シミュレーション①
まずは、一般的な相続不動産である戸建の登録免許税を計算しましょう。
1. 全ての不動産の評価額を合算する :15,836,914円+678,234円=16,515,148円
2. 1,000円未満を切り捨てる :16,515,000円・・・(課税標準額)
3. 課税標準額に税率(0.4%)を掛ける:16,515,000円×0.4%=66,060円
4. 100円未満を切り捨てる :66,000円
以上のとおり登録免許税は、66,000円になります。
2-2-2.登録免許税の計算シミュレーション②
マンションのような区分建物は、部屋の部分である専有部分と、土地の持分割合である敷地部分を合算して計算します。
敷地(土地)の評価額は次のように計算します。
固定資産税評価額 土地:158,369,147円 専有部分:678,234円の場合〉
1. 土地評価額に敷地権割合を掛ける :158,369,147円×(2100/120000)=2,771,460円
2. 全ての不動産の評価額を合算する:2,771,460円+678,234円=3,449,694円
3. 1,000円未満を切り捨てる :3,449,000円
4. 課税標準額に税率(0.4%)を掛ける:3,449,000円×0.4%=13,796円
5. 100円未満を切り捨てる :13,700円
以上のとおり登録免許税は、13,700円になります。
2-2-3.登録免許税の計算シミュレーション③
建物の増改築、地積の更正・変更、土地の合筆・分筆などにより、課税明細書の地積と登記簿の地積が異なることがあります。
• 登記簿上の地積の方が課税明細書記載の地積よりも大きい場合
基本的には課税明細書に記載されている現況の固定資産税評価額から、
1㎡単価の価額を計算して、それに登記簿上の地積を掛けて不動産の価額を計算します。
• 登記簿上の地積の方が課税明細書に記載の地積よりも小さい場合
計算せずに課税明細書に記載されている金額を使いますが、法務局の確認が必要です。
原則として、課税明細書に記載されている金額を基に課税標準額を算出しますが、例外的なケースである場合は、登記申請先の法務局への確認が必要です。
登録免許税の過不足は、別途手続きが必要となる場合があります。 課税明細書と登記簿の地積が異なる場合は、必ず事前に法務局に確認してください。
〈一戸建 登記簿上の地積:65.27㎡ 課税明細書上の地積:62.27㎡ 固定資産税評価額 土地:15,836,914円 家屋:678,234円の場合〉
1. 土地の評価額を計算する :15,836,914円÷62.27=@254,326円
@254,326円×65.27=16,599,858円
※@の数字は1㎡あたりの価額を表しています。
2. 全ての不動産の評価額を合算する:16,599,858円+678,234円=17,278,092円
3. 1,000円未満を切り捨てる :17,278,000円
4. 課税標準額に税率(0.4%)を掛ける:17,278,000円×0.4%=69,112円
5. 100円未満を切り捨てる :69,100円
以上のとおり登録免許税は、69,100円になります。
2-2-4.登録免許税の計算シミュレーション④
相続不動産に私道や公衆用道路が含まれている場合があります。
私道や公衆用道路の固定資産評価証明書を取得すると、価格の欄に「非課税」とだけ記載されていることがあります。これは「固定資産税が非課税」ということです。非課税不動産であっても、所有権移転登記の際に登録免許税は課税されます。
公衆用道路の不動産の価額は、「近傍宅地の1㎡あたりの価額×地積×100分の30」で計算します。近傍宅地の1㎡あたりの価額については、不動産の所在地によって異なりますので、事前に管轄の法務局に確認しましょう。
乙土地(公衆用道路)の地積7.89㎡ 非課税 近傍宅地は甲土地〉
1. 乙土地の評価額を計算する :15,836,914円÷65.27=@242,636円
@242,636円×7.89=1,914,398円
1,914,398円×0.3=574,319円
※@の数字は1㎡あたりの価額を表しています。
2. 全ての不動産の評価額を合算する:15,836,914円+574,319円=16,411,233円
3. 1,000円未満を切り捨てる :16,411,000円
4. 課税標準額に税率(0.4%)を掛ける:16,411,000円×0.4%=65,644円
5. 100円未満を切り捨てる :65,600円
以上のとおり、登録免許税は、65,600円になります。
2-3.相続登記を一括申請すると登録免許税は軽減される?
相続による所有権移転登記は、原則として、登記の目的と登記原因に応じて1つの不動産ごとに申請しなければならないとされています(不動産登記令第4条本文)。ただし、例外的に、不動産を管轄する法務局が同じ法務局であり、登記の目的(所有権移転等)と登記原因(相続等)が同じで、同じ相続人が同時に登記申請する場合には、複数の不動産を一括して相続登記することができます(「一括申請」といいます。不動産登記令第4条但書)。
この場合、登録免許税が安く済むケースがあります。
それでは、一括申請の場合と別々に申請した場合とで、登録免許税にどのくらい差が生じるか計算してみましょう。
| 土地を3筆相続した場合 | ||
|---|---|---|
| A土地 | B土地 | C土地 |
| 15,836,914円 | 15,836,914円 | 15,836,914円 |
■一括申請した場合
登録免許税は以下の計算で求められます。
1. 全ての不動産の評価額を合算する:15,836,914円×3=47,510,742円
2. 1,000円未満を切り捨てる :47,510,000円
3. 課税標準額に税率(0.4%)を掛ける:47,510,000円×0.4%=190,040円
4. 100円未満を切り捨てる :190,000円
このように一括申請した場合の登録免許税は、190,000円になります。
■別々に申請した場合
登録免許税は以下の計算で求められます。
1. 1筆の不動産の評価額 :15,836,914円
2. 1,000円未満を切り捨てる :15,836,000円
3. 課税標準額に税率(0.4%)を掛ける:15,836,000円×0.4%=63,344円
4. 100円未満を切り捨てる :63,300円
5. 3筆分を計算 :189,900円
このように別々に申請した場合の登録免許税は、189,900円になります。
一括申請する場合と別々に申請する場合との差額は100円となります。
では、評価額が低い不動産が複数ある場合はどうでしょう。
| 評価が低い土地を3筆相続した場合 | ||
|---|---|---|
| A土地 | B土地 | C土地 |
| 96,385円 | 96,385円 | 96,385円 |
■一括申請した場合
登録免許税は以下の計算で求められます。
1. 全ての不動産の評価額を合算する :96,385円×3=289,155円
2. 1,000円未満を切り捨てる :289,000円
3. 課税標準額に税率(0.4%)を掛ける :289,000円×0.4%=1,156円
4. 100円未満を切り捨てる :1,100円
このように、一括申請した場合の登録免許税は、1,100円になります。
■別々に申請した場合
登録免許税は以下の計算で求められます。
1. 1筆の不動産の評価額 :96,385円
2. 1,000円未満を切り捨てる :96,000円
3. 課税標準額に税率(0.4%)を掛ける :96,000円×0.4%=384円
4. 登録免許税の最低価額 :1,000円
5. 3筆分を計算 :3,000円
このように、別々に申請した場合の登録免許税は、3,000円になります。
以上のとおり、一括申請した場合と別々に申請した場合との登録免許税の差額は1,900円となり、評価額が低い不動産の場合は、まとめて登記申請をしたほうがお得になることがあります。
3.相続登記にかかる登録免許税の免税措置とは
平成30年度の税制改正により、相続による土地の所有権の移転の登記について、登録免許税の免税措置が設けられました。また、令和3年度の税制改正により、免税措置の対象に一定の要件を満たした所有権の保存登記が追加されると共に、免税措置の対象期間が1年延長され、令和4年3月31日までの相続登記が適用の対象となっています。(参考:法務局ホームページ「相続登記の登録免許税の免税措置について」)
この制度は、所有者不明土地問題の解決に向けて「相続登記の義務化」に先立って設けられた措置であると考えられています。
相続登記に対する登録免許税の免除措置の対象となる不動産は土地のみです。建物は対象外となります。
相続登記にかかる登録免許税の免税措置は、以下の2つの場合に適用されます。
2. 市街化区域外で法務大臣が指定する土地で相続登記を申請した場合
それでは、免税要件や適用期間、免税を受けるための方法について解説します。
3-1.相続登記に対する登録免許税の免税要件
・相続により土地を取得した方が相続登記をしないで死亡した場合
相続により土地を取得(相続人が遺贈により土地を取得した場合も含みます。)した個人がその相続登記を行わないまま死亡した場合、令和4年3月31日までに、その亡くなった個人の名義とするための相続登記を申請すれば、登録免許税が免除されます。
具体例を挙げて解説します。
2. 父は土地の相続登記をしなかった。
3. 父が令和1年12月1日に亡くなり、長男が土地を相続した。(2次相続)
4. 長男が令和2年2月1日に、祖父から父の名義にする相続登記と父から長男の名義にする相続登記を申請。
この場合、祖父から父の名義にする相続登記を申請する際の登録免許税は、免税措置により免除されます。これに対し、父から長男の名義にする相続登記は、通常どおり、登録免許税が課せられます。
ただし上記の例のように、数回にわたって相続が発生している場合には、利害関係者が多数に及んでいて、非常に専門的な手続きが必要となる可能性があります。詳しくは、相続手続きを専門としている司法書士事務所にご相談されることをお勧めします。
・法務大臣が指定する土地で相続登記を申請した場合
市街化区域外で法務大臣が指定する土地のうち、不動産の価額が10万円以下の土地の相続登記は、登録免許税が免除となります。
こちらは3つの要件全部を満たしていれば、登録免許税が免除となります。その3つの要件は以下のとおりです。
- 市街化区域外の土地であること
- 法務大臣が指定する土地であること
- 不動産の価額が10万円以下であること
また、令和3年度の税制改正により、土地の表題部所有者の相続人が受ける所有権の保存登記も新たに免税措置の対象になりました。
市街化区域は市町村の都市計画課などで確認できます。法務大臣指定の土地かどうかについては、当該土地を管轄する法務局のホームページで確認できます(法務局・地方法務局のホームページ・連絡先等001287601.pdf (moj.go.jp))。
不動産の価額は、固定資産税評価額です。1筆の土地の固定資産税評価額が10万円以下の場合、免除となります。また、まとめて相続登記する場合には、評価額の合計額で判断するのではなく、1筆の土地毎に10万円以下か否かを判断します。
3-2.免税の適用期間
相続登記にかかる登録免許税の免税措置の適用期間は、相続により土地を取得した個人が登記をしないで死亡した場合と、少額の土地を相続により取得した場合とで異なります。
前者は、平成30年4月1日から令和4年3月31日までの間に登記申請した相続登記に適用されます。これに対して、後者は、平成30年11月15日から令和4年3月31日までの間に申請した登記に適用されます。
なお平成30年4月からの免税措置ですが、それ以前に亡くなった方についての相続登記にも適用されます。相続登記をしないまま放置しているのなら、是非この機会に相続登記を済ませておきましょう。
また、免税措置がご自身の場合に当てはまっているかどうか迷われるかと思います。判断に迷っているなら、まずは相続手続きを専門としている司法書士にご相談されることをお勧めします。
3-3.免税措置を受けるには申請書の記載が求められる
登録免許税の免税措置の適用を受けるためには、登記申請書に以下の文言を記載する必要があります。
租税特別措置法第84条の2の3第1項により非課税
・少額の土地を相続により取得した場合の登録免許税の免税措置(所有権の保存登記もこちらとなります)
租税特別措置法第84条の2の3第2項により非課税
免税措置を受けるために特に必要な書類等はありませんが、申請書にこれらの法令の条項の記載がない場合、免税措置は受けられませんのでご注意ください。
4.相続登記にかかる登録免許税の納付方法
次に、登録免許税の納付方法について解説します。
4-1.納税期限について
相続登記にかかる登録免許税の納税期限は、登記を受ける時とされています。登録免許税は、相続登記を申請する時に、申請書に、金融機関等で納付した領収書、または収入印紙を貼り付けて申請しなければなりません。現金を金融機関等で納付するか、収入印紙を買って納付します。申請の際に、領収書か収入印紙を貼り付けていなければ、登記申請は却下されます。
4-2.現金で納付を行う
登録免許税を現金で納付する場合は、金融機関に出向き、登録免許税(国税)納付用の納付書に所定の必要事項を記入して窓口に提出し、登録免許税を支払います。手続きが済むと領収証書が交付されます。法務局に現金で納める事はできません。登記申請書にその領収証書を貼り付けて、法務局に申請します。
4-3.収入印紙での納付が可能なケース
また、登録免許税額が30,000円以下の場合は収入印紙で納付することが認められています。収入印紙は法務局、郵便局で購入可能です。しかし、実務上は登録免許税額が30,000円を超える場合でも、収入印紙で納付するケースが多いようです。念のため、納付方法については事前に法務局に確認してください。
5.相続登記ではなく生前贈与する場合の登録免許税
「生前贈与」とは、贈与者が生前に自己の財産を無償で相手に与えることをいいます。生前贈与は、多く場合、親族間で相続税対策や遺産分割対策を目的として行われます。
不動産を生前贈与したときは、贈与を原因とする所有権移転登記をすることができます。贈与による所有権移転登記の登録免許税の税率は、登録免許税法上の「その他の原因による移転の登記」にあたり、2%です。
6.相続登記で登録免許税以外にかかる費用
相続登記を申請するには、登録免許税以外に、法務局に提出する書類の取得費用など、別途費用がかかります。主なものは、戸籍謄本等の提出書類の取得費用、不動産の調査のための登記事項証明書(登記簿謄本)の取得費用などがあります。相続登記を司法書士に依頼する場合は、司法書士への報酬が必要になります。
相続登記で登録免許税以外にかかる費用は、「相続登記にかかる費用は?自分で行う/専門家に依頼する際の報酬相場を紹介」で詳しく解説しておりますので、こちらをご参照ください。
7.事業用不動産の登録免許税は必要経費として扱える
なお、相続によって取得した事業用不動産について、相続登記時に支払った登録免許税は、不動産所得の金額の計算上、必要経費に算入することができます。
例えば、アパート賃貸業を営んでいた父親が亡くなり、相続人の長男は事業を引き継ぐことになりました。その賃貸アパートの相続登記の際に支払った登録免許税や不動産取得税等は、必要経費に算入することができます。
8.まとめ
相続登記をする際に必要な登録免許税は、土地の価格によっては、相続人にとって決して安くはない費用となります。登録免許税の負担は、昨今社会問題となっている所有者不明土地の増加している原因の一つといえるでしょう。
この記事で触れましたように、所有者不明土地の発生を防ぐために、様々な免税措置が設けられています。また、2021年4月に不動産登記法が改正され、相続登記の申請が義務化されることを受けて、政府は登録免許税の負担を和らげる措置の導入を新たに検討しているようです。
ご自身の相続登記について、免税措置を受けられるのかどうか、相続登記や相続手続きの進め方、費用や期間など、相続手続き専門の司法書士法人チェスターまでご相談ください。疑問点の解決、手続きの代行など、あなたのご希望に沿ってご対応します。
今まで見たページ(最大5件)
関連性が高い記事
カテゴリから他の記事を探す
-
- その他
- 相続対策編
- 相続登記編
- 相続税Q&A
- 税務調査編
- 身分関係編
- 農地編
- 住宅取得資金編
- 対策一般編
- 所得税編
- 相続税
- 相続手続き編
- 葬儀関係編
- 計算方法編
- 退職金編
- 遺産分割編
- その他
- 保険編
- 財産評価
- 相続法務編
- 遺産分割編
- 遺言編
- 非上場株式編
- 事業承継税制編
- 国際税務(贈与税)編
- 贈与税
- 相続税編
- 預貯金編
- 各種控除編
- 名義変更編
- 成年後見編
- 精算課税編
- 相続税Q&A
- 一般動産編
- 国際相続編
- 国際税務(相続税)編
- 民法一般編
- 贈与税法一般編
- 税務一般編
- その他
- 保険編
- 小規模宅地等の特例編
- 特別受益編
- 申請手続編
- 財産評価編
- その他
- 借地権編
- 手続き編
- 相続放棄編
- 贈与税編
- その他
- 債務編
- 物納・延納編
- 非公開裁決事例解説
- 国外財産編
- 申告手続き編
- 土地一般編
- 相続税法一般編
- その他
- 山林・原野編
- 広大地編
- 建物編
- 有価証券編
- 葬式費用編
- その他
















