原戸籍(改製原戸籍・はらこせき)とは!?
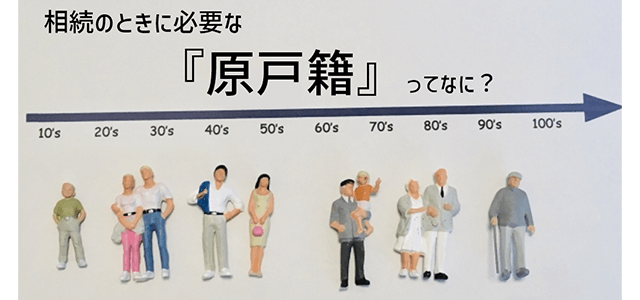
原戸籍(はらこせき)と言う言葉、聞いたことはありますか?正確には改正原戸籍(かいせいげんこせき)と呼ばれるものですが、これは相続の際必要となってくるものの一つです。
戸籍法の改正によって戸籍の様式が変更されるたびに、記載される情報が少しずつ変わってくる場合があります。
原戸籍というのは、もともとの戸籍の事で、変更される前の元の戸籍ということです。相続の際には、現行の戸籍謄本の他に、この原戸籍も必要となってきます。
被相続人が生まれてから死亡するまでのすべての戸籍情報が必要となるというわけです。戸籍の様式が変更になると、その時に効力のある事項だけが転載されますので、その時点で特に効力のないと見なされる情報は新しい戸籍に記載されないのです。
すべての戸籍情報を知るため、その原戸籍も取得して相続手続きを行わなければいけないと言うわけです。相続を行う際には、戸籍謄本の他に、この原戸籍もきちんと取り寄せて作業するようにしましょう。
役所内のコンピューターにデータとしてあるものが、「現在戸籍」で、それまでの紙の戸籍簿のことを「改製原戸籍」と言います。つまり、「改製原戸籍」は、いわば、「古い戸籍」という認識で概ね間違いないかと思います。
今まで見たページ(最大5件)
関連性が高い記事
カテゴリから他の記事を探す
-
相続法務編
















