贈与税の速算表を使って試算しよう。一般税率と特例税率の違いは?
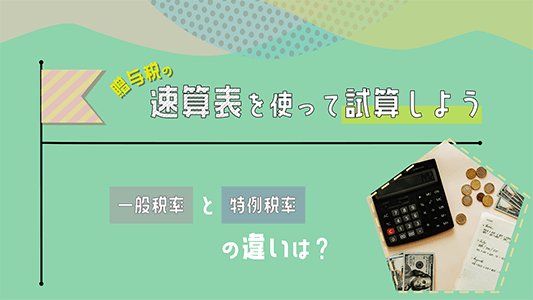
贈与税の速算表を活用すると、財産を譲り受けたときの税額を計算できます。贈与税の概要や、暦年課税制度で用いられる特例税率・一般税率の違いも確認しましょう。相続時精算課税制度や、贈与税を課税されないケースについても解説します。
1.暦年課税の贈与税の仕組み
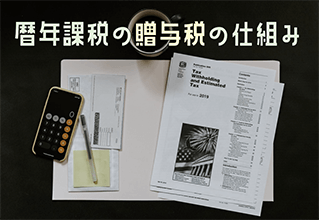
速算表を使って贈与税額の計算をするには、暦年課税制度の仕組みを知ることが大切です。贈与税の基礎知識や控除額について見ていきましょう。
1-1.贈与税とは
贈与税は、1月1日~12月31日の間に受けた贈与に対して課される税金です。自動的に課されるわけではないため、課税対象となる贈与を受けた場合、自ら申告し納税しなければいけません。
申告期限は贈与を受けた翌年の2月1日~3月15日です。申告した税額は基本的に一括で納税します。しかし贈与税は、何年かに分けて納税する延納も可能です。延納の希望は、申告の期限までに税務署へ申請書を提出し許可を得ます。
また専用サイトを利用したクレジットカード納付、インターネットバンキング等による電子納付(登録方式)、ダイレクト納付といった支払方法もあります。
1-2.基礎控除額を引いた額が課税価格
贈与税は受け取った全ての贈与に課税されるわけではありません。1年間の贈与額から基礎控除額『110万円』を引いた『課税価額』に対して税金がかかります。
そのため1年間の贈与額が110万円以下であれば、贈与税は課税されません。税金がかからないため、贈与税の申告も不要です。
ただし暦年贈与の基礎控除額は、贈与した人ではなく贈与を受けた人(受贈者)ごとに計算するものである点に注意しましょう。例えば両親のそれぞれが1人の子どもへ110万円ずつ贈与すると、子どもが1年間に受け取るのは220万円です。
このケースでは110万円を超えるため、贈与税が課税されます。今年は父から110万円、来年は母から110万円贈与を受けるというケースでは贈与税は非課税です。
2.贈与税の税率

贈与をした人と受けた人の関係性により税率は異なります。一般税率と特例税率が適用されるケースと、税率の速算表・計算方法を解説します。
2-1.一般税率の贈与税速算表
一般税率が適用されるのは、直系尊属以外から贈与を受けるケースです。例えば夫婦間・兄弟姉妹間で贈与された場合、一般税率が適用されます。
また直系尊属であっても、受け取る子どもや孫が20歳未満だと、適用されるのは一般税率です。一般税率は下記の速算表に従い計算します。
| 課税価格 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 200万円以下 | 10% | - |
| 300万円以下 | 15% | 10万円 |
| 400万円以下 | 20% | 25万円 |
| 600万円以下 | 30% | 65万円 |
| 1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
| 1,500万円以下 | 45% | 175万円 |
| 3,000万円以下 | 50% | 250万円 |
| 3,000万円超 | 55% | 400万円 |
出典:No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)|国税庁
2-2.特例税率の贈与税速算表
一般税率より税率が低い特例税率は、直系尊属から贈与を受けたときに適用されます。贈与を受ける子どもや孫が、贈与される年の1月1日に20歳以上であれば利用できます。
例えば父母から子どもへ祖父母から孫へ、といった贈与が対象です。対象となる贈与は下記の速算表を使い贈与税を計算します。
| 課税価格 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 200万円以下 | 10% | - |
| 400万円以下 | 15% | 10万円 |
| 600万円以下 | 20% | 30万円 |
| 1,000万円以下 | 30% | 90万円 |
| 1,500万円以下 | 40% | 190万円 |
| 3,000万円以下 | 45% | 265万円 |
| 4,500万円以下 | 50% | 415万円 |
| 4,500万円超 | 55% | 640万円 |
また課税価格が300万円を超えると、申告書とともに直系尊属からの贈与であることを証明する戸籍謄本や抄本の提出が必要です。
出典:No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)|国税庁
参考:平成27年以降に父母などから財産の贈与を受けた場合はご注意ください(暦年課税の場合)|国税庁
2-3.課税価格に税率をかけて控除額を引く
贈与税の速算表を用いて税額を求めるには『課税価格×税率-控除額』で計算します。例えば夫から1,000万円の贈与を受けたときの課税価格は890万円です。
一般税率が適用されるため税率40%、控除額125万円で計算します。『890万円×40%-125万円=231万円』です。
特例税率でも基本的な計算方法は同じです。1,000万円を贈与されたとき、課税価格890万円にかかる税率と控除額を速算表で確認しましょう。『890万円×30%-90万円=177万円』と求められます。
2-3-1.一般税率、特例税率が混在する計算
1年間に一般税率と特例税率の両方が適用される贈与を受ける場合もあるでしょう。例えば父から800万円・配偶者から200万円の贈与を受けたケースで計算します。課税価格は『(800万円+200万円)-110万円=890万円』です。
次に一般税率を計算します。『890万円×40%-125万円=231万円』で、贈与全体に占める一般税率の割合で計算すると『231万円×200万円÷1,000万円=46万2,000円』です。
特例税率は『890万円×30%-90万円=177万円』で、一般税率と同じように贈与全体に占める特例税率の割合を計算すると『177万円×800万円÷1,000万円=141万6,000円』です。
最後に両者を足して『46万2,000円+141万6,000円=187万8,000円』と求められます。
3.生前贈与を行う税制上のメリットと注意点
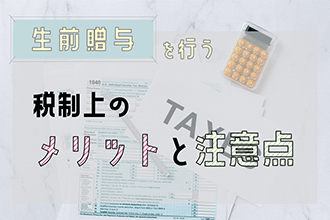
生前贈与には節税につながるメリットがあるといわれています。ただし気を付けなければいけない点もあるため、よく確認した上で利用しましょう。
3-1.相続時の税負担を軽減
相続税の負担を軽くする方法として生前贈与が用いられます。相続税も贈与税と同じく、基礎控除内であれば課税されません。
ただし基礎控除は2015年から『3,000万円+(600万円×法定相続人の数)』とそれ以前より減額されており、相続税の対象範囲が拡大しているのです。そのため生前贈与を用いた負担軽減が注目されています。
3-2.暦年課税制度を利用する
生前贈与で暦年課税制度を利用すれば、複数年にわたって贈与することで相続時に課税される金額を減らせます。暦年課税制度では、1年に110万円までの贈与は非課税です。単純に計算するなら、10年間続けることで1,100万円の財産を非課税で移動できます。
なお、110万円の基礎控除額は受贈者ごとに設定されているため、受贈者が複数いればそれだけ多くの財産を移せる計算です。子ども3人に対して1年間に110万円ずつ贈与すれば、330万円が非課税で渡せます。
3-3.贈与契約書の作成は欠かせない
暦年課税制度を用い細かく贈与する際には『贈与契約書』の作成が欠かせません。2通作成し、贈与する側・受ける側で1通ずつ保管します。
贈与は口頭のみでも成立しますが、契約書がなければ契約内容を客観的に示せません。いつ誰とどのような内容の贈与契約を結んだのかが分かる契約書があれば、税務調査でも贈与の事実を示せます。
例えば毎年100万円前後の贈与を10年間受け、総額が1,000万円になったとします。このとき最初から1,000万円の贈与を10年にわたり行う契約だったとみなされると、1,000万円の贈与に対して課税される可能性があるのです
都度契約書を作成しておけば、このような事態の回避にも役立つでしょう。不安がある場合は『税理士法人チェスター』など、税理士への相談がおすすめです。
4.相続時精算課税制度との違い
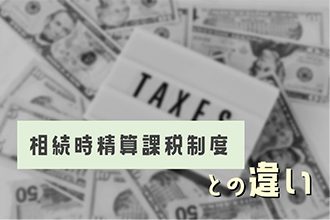
贈与税の課税方法には、暦年課税制度のほかに『相続時精算課税制度』があります。相続時精算課税制度はどのような仕組みなのでしょうか?
4-1.2,500万円まで贈与税なし
相続時精算課税制度とは税務署へ届出を行うことで、2,500万円までの贈与が非課税になる制度です。届出は最初の贈与を受けた翌年の2月1日~3月15日の間に行います。
2,500万円の上限は贈与者ごとに設定されるものです。そのため祖父・祖母・父・母からそれぞれ2,500万円を受け取ったとしても、贈与税はかかりません。
ただし一度相続時精算課税制度を選択した贈与者とは、暦年課税制度へ戻せない点に注意が必要です。また相続時精算課税制度を利用すると、相続時に適用される可能性がある『小規模宅地の特例』を利用できません。
居住用の宅地の評価額を80%減額できる制度のため、宅地の相続が想定される場合にはよく検討してから選びましょう。
4-2.2,500万円を超えた部分は20%の贈与税
税務署へ届出をした贈与者との間で、2,500万円以上の贈与があった場合、超えた分には『20%』の贈与税が課されます。さらに相続時には贈与財産を受け取ったときの価額で相続財産に加え、相続税を計算する仕組みです。
あらかじめ支払った贈与税がある場合には相続時に相続税額から差し引かれ、相続税の方が少ないときには差額が還付されます。
その他注意が必要なのは、贈与を受けると金額にかかわらず申告しなければいけない点です。暦年課税制度に比べると、手続きが煩雑になりやすい点を覚えておきましょう。
5.贈与税がかからないケースもある
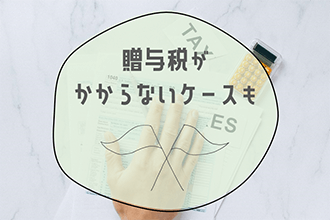
用途によっては贈与税がかからないケースもあります。非課税で贈与したいときに利用を検討するとよいでしょう。
5-1.扶養義務者から子や孫へ必要な都度の贈与
通常必要と考えられる『生活費』のために扶養義務者が行う贈与は非課税です。扶養義務者とは、配偶者・直系血族・兄弟姉妹を指します。
例えば子どもの塾の費用を祖父母が負担してくれた、公共交通機関の発達していない地域で子どもが親へ自動車を購入した、といったケースは生活に必要な都度の贈与と考えられ、金額にかかわらず贈与税が課されることはありません。
ただし贈与税がかからないのは、直接生活費に使った場合です。教育費という名目で贈与を受けたとしても、預金したり株や不動産の購入資金に充てたりすると、贈与税がかかります。
5-2.上限ありで住宅資金や教育資金など
父母や祖父母など直系尊属からの贈与であれば、一定金額が非課税になる特例があります。『住宅資金』の場合、居住する住宅の取得費用として用いるなら、最高3,000万円まで非課税です。ただし、期間が2015年1月1日~2021年12月31日と決まっています。
『教育資金』や『結婚・子育て資金』の一括贈与は、契約する金融機関を通して非課税申告書を税務署へ提出することで利用が可能です。
教育資金は1,500万円、結婚・子育て資金は1,000万円が上限です。どの特例も適用には条件があり、申告書を提出しなければいけません。また暦年課税制度もしくは相続時精算課税制度と併用できます。
ほかに贈与後3年以内に相続が発生しても、相続財産に加算されない点も特徴です。
参考:No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税|国税庁
参考:No.4510 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税|国税庁
参考:No.4511 直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税|国税庁
5-3.配偶者への不動産贈与は最大2,000万円
自らが居住する不動産や不動産の取得費用であれば、基礎控除の110万円のほかに、配偶者控除で最大2,000万円までが非課税になる特例もあります。継続した婚姻関係が20年以上の夫婦に適用される特例です。
夫婦間の所有財産の差が大きいと、相続時の税負担が大きくなる可能性があります。リスクを排除するために、あらかじめ財産の移動を行いたいと計画しているときに有効な方法です。
参考:No.4452 夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除|国税庁
6.早見表を使えば試算は簡単に可能
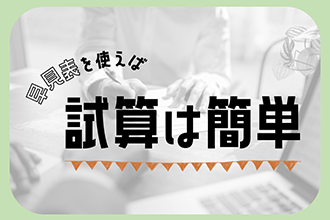
暦年課税制度の贈与税を計算する際には、速算表を参考にしながら『課税価格×税率-控除額』で計算しましょう。直系尊属からの相続に適用される特例税率と、その他の相続で用いる一般税率があります。
計算そのものは簡単にできますが、暦年課税制度と相続時精算課税制度のどちらを利用するべきか、判断が難しいと感じることや、他の制度の利用について詳しく知りたいとこともあるでしょう。
そのようなときには『税理士法人チェスター』への問い合わせがおすすめです。相続税との関係も考慮しつつ、効果的な生前贈与について相談するのに役立つでしょう。
今まで見たページ(最大5件)
関連性が高い記事
カテゴリから他の記事を探す
-
贈与税編
















