生前贈与で現金300万円を手渡しはNG?注意点と非課税になる制度

生前贈与で現金300万円を受け取る場合には、どのような方法がよいのでしょうか?贈与を受けたときにかかる贈与税は、受け取り方により金額が変わります。節税につながりやすい方法を確認しましょう。税務調査で重視される項目も解説します。
この記事の目次
1.生前贈与の目的

生きているうちに財産を贈与するのには、どのような目的があるのでしょうか?生前贈与を行う代表的な目的を見ていきましょう。
1-1.子や孫世代に資産を活用してもらう
生前贈与の目的としてまず挙げられるのは、子や孫など若い世代が資産を活用しやすくすることです。若い世代は結婚費用・子どもの教育費・住宅の購入など、大きなお金を使う機会が多くあります。
しかし自分たちの持っている資金だけでは、予算に限度があるでしょう。そこで父母や祖父母世代の資産を贈与により若い世代へ移転させ、活用してもらおうという狙いがあります。
子や孫世代は贈与により、自分たちだけでは手の届かなかった物件の購入や上質な教育を実施できます。このように大きなお金が動きやすい状況になれば、消費の活性化にもつながりやすいでしょう。
1-2.相続税の税率と支払う税金の目安
贈与しなかった財産は所有者の死後、相続により引き継がれます。このとき相続税は、単純に各相続人が引き継いだ遺産額に課せられるわけではありません。
まず遺産の総額から基礎控除が差し引かれ、その残りを相続した割合に応じて案分します。そこで出た数字を下記の表に当てはめ、定められた控除額を引いた後、税率を乗じて相続税額を求めるのです。
| 法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 10% | - |
| 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
求めた相続税より生前贈与に課せられる贈与税の方が少なければ、生前贈与は節税につながります。
2.1人あたり300万円を贈与する際の税金
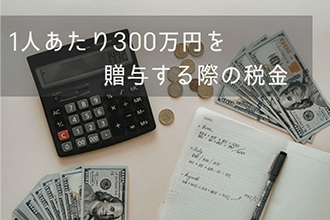
300万円の贈与を受ける際、贈与税は具体的にいくらかかるのか計算しましょう。贈与税の計算に必要な暦年課税の基礎控除について、また具体的な贈与税額の計算について解説します。
2-1.暦年課税は110万円を超えた分に課税
暦年課税で生前贈与を実施するにあたり、基礎控除として『110万円』を差し引けます。そのため、贈与の金額が1月1日から12月31日までの1年間で110万円以下であれば、贈与税は非課税です。
その際には申告も不要のため、贈与を受けても何もする必要はありません。また300万円を贈与で受け取った場合には、贈与税は110万円を差し引いた190万円に課されます。
暦年課税の基礎控除は、贈与を受ける人の人数で計算されるため、将来相続人になる人が多いほど、節税につながりやすい仕組みです。
2-2.300万円の贈与にかかる贈与税は?
贈与税の計算をする際には、父母や祖父母など直系尊属から受けた贈与に適用される特例税率か、その他の贈与に適用される一般税率かで税率が異なります。
どちらの税率も10~55%で設定されていますが、特例税率の方が緩やかに上昇するのが特徴です。ただし300万円の贈与で課税対象となるのは190万円のため、特例税率でも一般税率でも10%で計算します。その結果かかる税金は『19万円』です。300万円に対する19万円は約6.3%です。
参考:No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)|国税庁
3.生前贈与の注意点
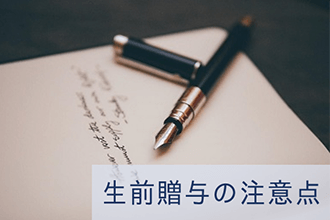
生前贈与を効果的に行うことで、将来的に支払う相続税を低く抑えることが可能です。しかし、生前贈与を実施するにあたり注意点もあります。あらぬ疑いをかけられないよう、注意点を知った上で実施することが大切です。
3-1.贈与契約書を作成しておこう
贈与は口約束のみでも法的には有効ですが、税務署に対して誰からいついくらの贈与を受けたのか証明できません。そのため『贈与契約書』を作成しておくと安心です。
贈与契約書に決まった形式はありませんが、最低でも『贈与の日時』『贈与者の氏名・住所』『受贈者の氏名・住所』『贈与する財産』『贈与する財産の引き渡し方法』『受贈者が贈与を受諾したという内容』が必要です。
特別な条件を満たすと贈与が実施されるなら、条件も記載しましょう。公証役場で確定日付をもらうと、さらに客観性の高い証拠として利用可能です。2通用意し、贈与者・受贈者がそれぞれ保管します。
また実際の贈与は、振り込みで実施すると記録が残るため望ましいでしょう。
3-2.相続開始前3年以内に贈与があった場合
生前贈与を受けていたとしても、相続開始前3年以内に受けたものである場合には、相続財産に加えられ、相続税が課される点も注意が必要です。節税目的で相続税を回避しないよう、3年の期限が設けられています。
既に支払っている贈与税分の金額は相続税額から差し引かれるため、二重に課税されることはありません。ただし相続開始前3年以内に受けた贈与であっても、相続税の対象とならないケースもあります。贈与を受けたけれど相続人ではない場合です。
このケースでは、加算対象ではないため相続税の納税は必要ありません。
3-3.「現金で直接渡して無申告」は厳禁
「現金で300万円を手渡ししてもらえば、無申告でもばれないのでは?」と考える人もいるかもしれません。しかし税務調査が入れば被相続人の口座を過去にさかのぼって確認されます。
そこに使途不明の300万円の出金があれば、相続税の課税対象と判断されるかもしれません。単に課税対象として扱われるだけでなく、原則として50万円までは15%、50万円を超える部分に20%の無申告加算税も課される可能性もあります。
さらに書類の偽造といった不正行為があれば、最高で50%の重加算税の納税も求められるのです。加えて納税が遅れたことに対するペナルティである延滞税も、完納までの日数に応じて加算されます。
4.生前贈与の税務調査で確認される重要項目
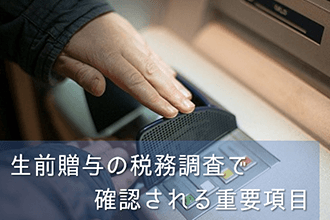
生前贈与の税務調査では、名義預金がないか確認されます。自分が知らないうちに名義預金になってしまっているケースもあるため、事前に注意しておかなければいけないポイントです。
4-1.知らなかったでは済まない名義預金
贈与が成立するには「贈ります」「受け取ります」という双方の合意がなければいけません。合意のないままに贈与が行われたような形式が取られていると、資産隠しを疑われかねません。
代表的なのが『名義預金』です。例えば親が子どもとの合意なしに口座を作り、贈与のつもりで入金していたとします。その後も口座を親が管理していれば、名義預金として扱われます。
形式的には子どもの預金ですが、口座の実質的な所有者は親のため、親の死亡時に相続財産に加算されるのです。故人の厚意で行われたことでも、ケースによっては資産隠しのための口座と判断されるかもしれません。
4-2.子や孫の名義の預金口座に入金する場合
子や孫の預金口座へ入金し贈与を受ける際には、必ずその旨を知らせてもらいましょう。預金口座の通帳や印鑑を子や孫が管理し、いつでも自由に使える状態になっていることもポイントです。
金融機関からの郵送物も、受贈者である子や孫へ届くようにしましょう。また贈与者が開設した口座を使用すると、名義預金と判断される可能性が高まるため、口座は受贈者が開設します。
贈与をするときには毎回契約書も作成しましょう。贈与者と受贈者の合意が明らかに分かる書類があれば、税務署へも贈与があったことを証明できます。加えて贈与税申告書の提出も、贈与の証明に役立つでしょう。
5.まとめてお金を贈与したい場合
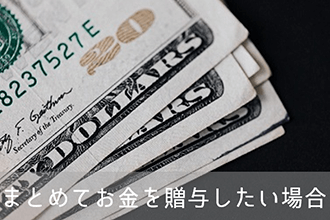
暦年課税の基礎控除を利用すれば、1年間に110万円まで非課税で贈与を受けられます。しかし資産が多かったり、早く受け取りたいと考えていたりと、より大きな金額を一度に贈与したい場合もあるでしょう。
そのようなときに役立つ、相続時精算課税制度について解説します。
5-1.相続時精算課税制度が活用できる
『相続時精算課税制度』には最大2,500万円の控除があります。暦年贈与を用い非課税で贈与しようとすると、20年間かけても2,200万円までしかできません。しかし相続時精算課税制度であれば、すぐに2,500万円まで贈与可能です。
制度の利用には税務署への届出が必要な点に注意しましょう。何もせずにいると、暦年課税制度が適用されてしまいます。
また相続時精算課税制度の控除は、贈与者が贈与する金額の合計から控除されるものです。そのため1人の孫へ父母や祖父母がそれぞれ2,500万円ずつ贈与しても、課税されません。
5-2.デメリットも存在する
一度に大きな金額を非課税で贈与できる相続時精算課税制度ですが、デメリットもあります。それは暦年課税制度を使えなくなる点です。
例えば祖父と孫との贈与に相続時精算課税制度を適用すると、この二者間での贈与は暦年課税制度の基礎控除を利用できません。後からの変更や、特定の年のみ暦年課税制度にするといった方法は不可能になります。
その他、相続時精算課税制度は贈与税が2,500万円まで非課税となりますが、将来相続が発生した場合、贈与した財産が相続財産に加えられるルールです。つまり最終的に相続税として課税されるため、必ずしも節税効果があるとはいえません。
6.使用目的により非課税で贈与できる制度

特定の使用目的がある資金を贈与すると、非課税になる制度もあります。どのような目的であれば非課税で贈与できるのでしょうか?
6-1.結婚・子育て資金の非課税の特例
2023年3月末まで適用期間が延長された『結婚・子育て資金の非課税の特例』を使用すると、1,000万円までの贈与を非課税にできます。贈与者は父母や祖父母などの直系尊属のみです。
また使用目的は挙式費用や、不妊治療も含めた出産費用・保育費用などに限られます。贈与を受けるには、金融機関と資金管理契約を結ばなければいけません。
加えて、贈与の事実が分かる契約書や受贈者の戸籍謄本などの必要書類をそろえ、税務署への提出も必要です。直接税務署へ出向く必要はなく、資金管理契約を結んだ金融機関を通して提出できます。
6-2.住宅取得等資金の非課税の特例
直系尊属からマイホームの購入資金を受け取るなら『住宅取得資金の非課税の特例』を利用すると、最大3,000万円まで税金がかかりません。2015年1月1日~2021年12月31日に贈与を受け、住宅を取得したケースが対象です。
契約締結の日付と住宅の機能性によって控除金額が異なるため、注意しましょう。また暦年課税制度や相続時精算課税制度との併用もできます。暦年課税制度なら3,110万円まで、相続時精算課税制度なら5,500万円まで非課税です。
この特例を利用するには、贈与を受けた翌年2月1日~3月15日に贈与税の申告をします。贈与税がかからないケースでも申告は必須です。
6-3.教育資金の非課税の特例
『教育資金の非課税の特例』を利用すると、教育資金として使う目的での贈与を最大1,500万円まで非課税にできます。教育資金に該当するのは、学校に支払う学費や教材費のほか、塾や習い事の費用も対象です。
ただし学校以外に支払う教育資金は、1,500万円のうち最大500万円までが非課税と定められています。特例を利用するには、結婚・子育て資金と同様に、金融機関と資金管理契約を結ばなければいけません。
金融機関を通して税務署への資料提出も必要です。受贈者が30歳になると原則として資金管理契約が終了する点は、結婚・子育て資金と異なります。
7.都度贈与でお金を援助すると非課税

贈与にかかる税金を非課税にする方法として『都度贈与』も利用可能です。都度贈与の基礎知識や、都度贈与とならない例を紹介します。
7-1.すぐに必要な分のみ受け取ること
生活に必要な資金をその都度受け取るのが『都度贈与』です。例えば子どもの学校の入学金を祖父母に出してもらった場合には、都度贈与のため非課税と判断されます。
都度贈与が適用されるのは、贈与者が配偶者・父母・兄弟姉妹など扶養義務者である場合です。扶養義務を果たすための贈与のため、贈与契約書の作成は不要です。
また贈与された資金は当初の目的に使用すれば非課税ですが、生活必需品以外の用途に資金を充てると課税されます。そのため教育費として受け取った資金を不動産取得の頭金にするケースでは、贈与税の支払いが必要です。
7-2.受け取ったお金を預金するのはNG
通常必要と考えられる資金であったとしても、数年分をまとめて受け取り、預金しておくと課税されます。ただし贈与契約書の作成が不要の都度贈与では、自己資金の預金と区別がつきにくいでしょう。
疑いをかけられないようにするには、贈与者から資金を受け取るのではなく、直接支払ってもらうことです。例えば教育費であれば、学校へ振り込んでもらいます。
加えて税務署から指摘を受けた場合に備え、明細書や領収書を保管しておくとよいでしょう。
8.どの方法が最適かは専門家に相談を
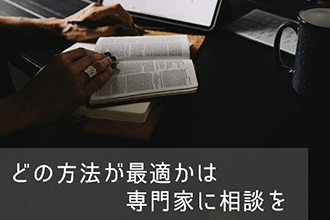
生前贈与は、暦年課税制度を用いると110万円の基礎控除を受けられるため、300万円の贈与を受けても実際の税率はおよそ6.3%です。課税対象部分に10%以上課税される相続税と比較し、節税につながりやすいでしょう。
また一度にまとまった金額の贈与を受ける際には、相続時精算課税制度の利用が役立ちます。特定の贈与者との間において、2,500万円までが非課税になる制度です。
ほかにも、特定の資金として使うときに定められた上限額まで非課税となる特例や、生活資金であれば非課税になる都度贈与もあります。どの方法が適切か判断が難しいと思ったら『税理士法人チェスター』へ相談しましょう。
今まで見たページ(最大5件)
関連性が高い記事
カテゴリから他の記事を探す
-
贈与税編
















