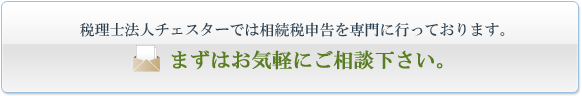法定相続分
法定相_続分とは、民法で定められている分割基準を示したものです。
基本的なパターンを分かりやすい図に示すと以下のとおりです。
なお配偶者は必ず相_続_人となります。
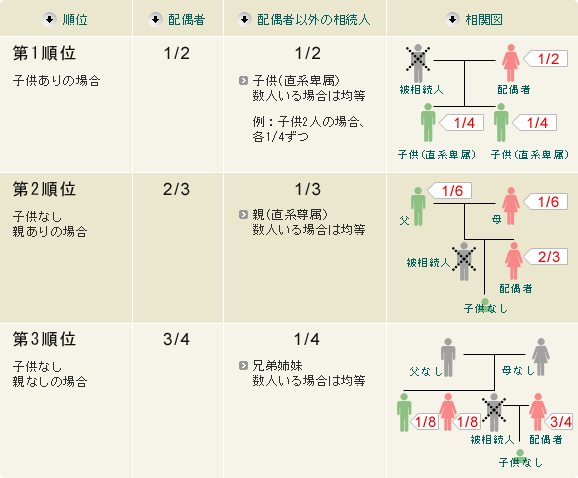
![]()
子は、被相_続_人である親と法律上の親子関係があれば、実子・養子、嫡出子・非嫡出子の区別なく相_続_人となります。子が第一順位であるという意味は、子が一人でもいればその者だけが血族として相_続_人となり親や兄弟姉妹は該当しないということです。
また、子がすでに死んでいたとすると、その子(孫)が親に代わって相_続します。
これを「代襲相_続」といいます。
![]()
血族の中に子(またはその代襲者)が一人もいないときは、直系尊属が相_続_人となります。まず親等のいちばん近い父母が相_続_人になり、父母がいないときは祖父母、次に曾祖父母というようにさかのぼっていきます。
※第一順位の者がいてもそのすべてが、(1)相_続欠格、相_続_人の廃除により相_続権を失った場合、(2)相_続放棄した場合、にも相_続_人となります。
![]()
第一順位及び第二順位の相_続_人がともにいなければ、兄弟姉妹が相_続_人となります。兄弟姉妹の子についても代襲相_続が認められています。ただし、子の場合とちがって、兄弟姉妹の子(つまり、甥・姪)までです。
※第二順位の者がいてもそのすべてが、(1)相_続欠格、相_続_人の廃除により権利を失った場合、(2)放棄した場合、にも相_続_人となります。
なお、民法に定める法定相_続分は、相_続_人の間で遺産分割の合意ができなかったときの遺産の取り分であり、必ずこの分割基準で遺産の分割をしなければならないわけではありません。
今まで見たページ(最大5件)
関連性が高い記事
カテゴリから他の記事を探す
-
相続法務編