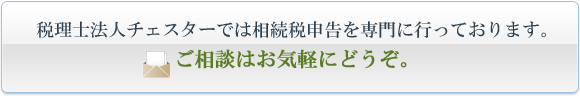相続税の算出方法
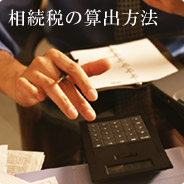
計算は一般的に次のような順序で行います。
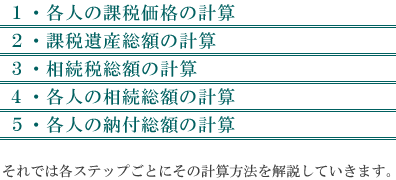
![]()
まずは各人が取得することになる遺産の課税価格を求めます。
|
課税価格= |
| 次のものが非課税財産の代表です。これらの財産は課税対象となりません。
1 墓所、仏壇、祭具など |
|
| 死亡前3年以内に被相続人から相続人に対して贈与された財産については、課税対象となりますので加算するのを忘れないようにしましょう。 |
![]()
上記1で求めた各人の課税価格を合計した後、基礎控除分を差し引いて課税資産総額を算出します。
|
課税遺産総額= |
| 基礎控除額は、5千万円+1千万円×法定相続人の数となっています。 |
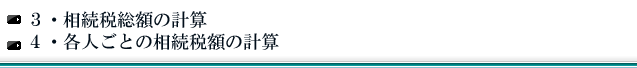
税額の総額は、法定相続人が法定の分割基準通りに遺産を取得したものとして算出した各人の税額を合計して求めます。 その税額の総額を実際に財産を取得した割合に応じて各人が負担することになります。
これは遺産分割の方法により税額が変動し、不当な遺産分割協議を防ぐために、いったん法定の分割基準分通りに取得したものと考えて税額の総額を計算することを目的としたものです。
全体の流れを図示すると以下のようになります。
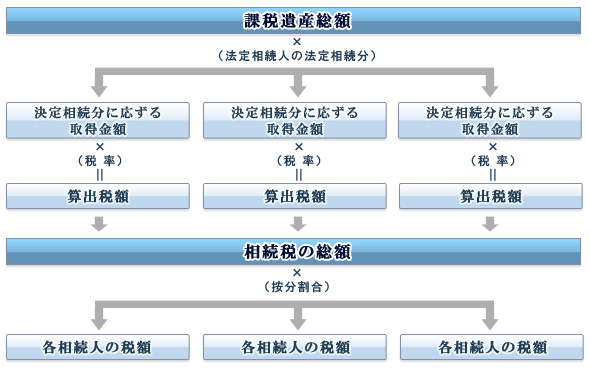
ここで使用される税率は次の速算表から求めます。
速算表
| 課税価格 | 税 率 | 控除額 |
| 1,000万円以下 | 10% | なし |
| 1,000万円超~3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 3,000万円超~5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 5,000万円超~1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 1億円超~3億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 3億円超 | 50% | 4,700万円 |
![]()
上記で算出した各人の税額を全額納付するわけではありません。
各人に下記の個別事情がある場合には、税額に各々下記の加算・控除を
行った金額が各人の納付すべき税額となります。
| 配偶者に対する軽減 配偶者は、法定相続分又は1億6,000万円以下の財産の取得であれば、税金はかかりません。 |
|
| 未成年者控除 20才未満の法定相続人がいる場合は、税額から次の金額が控除されます。 6万円×(20歳-相続開始時の年齢) |
|
| 障害者控除 障害者である法定相続人がいる場合は、税額から次の金額が控除されます。 6万円(特別障害者は12万円)×(70歳-相続開始時の年齢) |
|
| 贈与税額控除(暦年課税贈与税) 相続財産に加算された贈与財産に対する贈与税は、税額から控除されます。 |
|
| 贈与税額控除(相続時精算課税) 精算課税制度による贈与税が課せられているときは、その税額は税額から控除します。 また、税額から控除しきれない贈与税額があれば、その税額は還付されます。 |
|
| 相次相続控除 10年以内に続けて相続があると、2回目(第2次相続)では 1回目に払った金額の一部を差し引くことができます。 |
|
| 外国税額控除 海外に財産を持っていた場合、外国で日本の相続税にあたる税金を払うこともあります。 そうした場合は、外国で払った税金分を、日本の税金から差し引くことが出来るようになっています。 |
|
| 被相続人の兄弟や、代襲相続人ではない被相続人の孫、まったくの第三者などが、相続・遺贈により財産を取得した場合は、20%の税額の加算になります。 | |
![]()
実際には遺産の評価や各種特例の適用などを行い、税額を算出します。
正確な税額の算出を専門の税理士以外が行うのは難しいため、専門の税理士に依頼するのがいいでしょう。
今まで見たページ(最大5件)
関連性が高い記事
カテゴリから他の記事を探す
-
相続税編