死後事務委任契約でもしもの時に備える|かかる費用や注意点
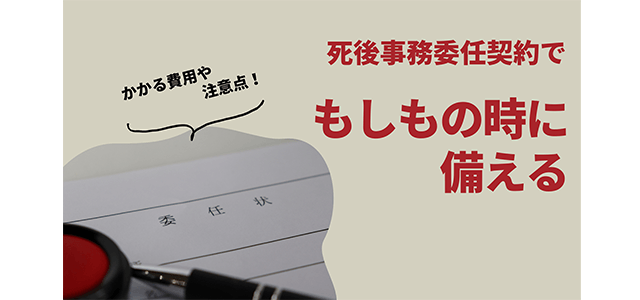
死後事務委任契約は、一般的には相続人が行う手続です。
死後事務委任契約を結ぶと、亡くなった後の葬儀や役所での手続、遺品の整理など、さまざまな事務手続を第三者に任せることができます。
しかし相続人がいない、もしくは疎遠であったり遠方に住んでいたりする場合には、信頼できる友人や専門業者に任せたほうが、希望するエンディングを迎えられると考える人もいるでしょう。
そのため、専門業者や弁護士などの法律家と死後事務委任契約を結ぶケースも増えていますが、専門業者や法律家との契約には当然ながら費用がかかります。
自らの死後において、必要となる事務手続のなかで不安に思っていることを洗い出し「所有する財産の範囲内で具体的に何をして欲しいのか」を、明確にした上での委任が大切です。
この記事の目次
1.死後事務委任契約とは?

死後事務委任契約とは、葬儀や役所への手続、クレジットカードの解約といった「亡くなった後に必要な事務手続を、生前に第三者へ委任しておく契約」です。
遺言の付言事項として、誰かを指名して亡くなった後の手続全般を一任することもできますが、この場合は一方的な意思表示となり、指名された側には法的拘束力が発生しません。対して死後事務委任契約は双方合意による契約であるため、より確実な方法と言えます。
なお、民法は委任の終了事由について以下のように定めていることから、死後事務委任契約は矛盾しているように感じられるかもしれません。
(委任の終了事由)
第六百五十三条
委任は、次に掲げる事由によって終了する。
一 委任者又は受任者の死亡
二 委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと。
三 受任者が後見開始の審判を受けたこと。
(引用:民法653条)
上記の条文について最高裁は以下のように判断し、死後事務委任契約の有効性を認めています。
自己の死後の事務を含めた法律行為等の委任契約がAと上告人との間に成立したとの原審の認定は,当然に,委任者Aの死亡によっても右契約を終了させない旨の合意を包含する趣旨のものというべく,民法六五三条の法意がかかる合意の効力を否定するものでないことは疑いを容れないところである。
死後事務委任契約の受任者となれるのは、親族はもちろん、知人や司法書士などの専門家と幅広く、さらには法人も対象です。
1-1.死後事務委任契約で委任できること
死後事務委任契約は、履行される段階では委任者が亡くなっており、内容を再確認したり変更したりできないため、事務の範囲は詳細に決めておかなくてはなりません。
死後事務委任契約で委任できること
- 法事関係:通夜、告別式、納骨、埋葬、永代供養の手続
- 行政関係:死亡届、年金受給停止、埋葬料や葬祭料の申請
- ライフライン関係:電気代やガス代などの公共料金の解約・精算
- 医療関係:医療費、入院費の精算
- 住居関係:家賃や管理費の精算、老人ホーム等の退去手続
- 財産関係:相続財産管理人の選任、遺品の整理・処分
- デジタル遺品関係:デジタル機器のデータ消去、デジタルサービス解約、SNSアカウント削除
- その他:親族・関係者への連絡など
1-2.死後事務委任契約を結ぶまでの流れ
死後事務委任契約は普段馴染みのない法律行為や専門家との接触が必要です。
締結までの流れを押さえておくことにより、スムーズな行動に移せます。
死後事務委任契契約の流れ
- 法律専門家への相談
- 委任内容の決定
- 死後事務委任契約書の作成
- 公正証書の作成
1-2-1.法律専門家への相談
死後事務委任契約について、司法書士などの法律専門家に相談します。まず法律専門家からヒアリングされるのは、死後事務委任契約を検討している理由や現況についてです。続いて「依頼したい死後事務について、遺言によるべきか、あるいは死後事務委任契約に盛り込むべきか」の判断を仰ぎ、今後の流れや費用についての説明を受けます。
1-2-2.委任内容の決定
死後事務委任契約の方向性が決まったら、履行すべき死後事務の範囲を明確にして委任内容を決定します。決めるべき委任内容は、たとえば葬儀の規模や内容はどうするのか、管理して欲しい遺品や必要な連絡先などです。
1-2-3.死後事務委任契約書の作成
決定した内容をもとに、死後事務委任契約書を作成します。受任者が司法書士などの法律専門家であれば、そのまま作成してもらうのが一般的です。また、受任者が法律専門家以外の場合は、受任者同席のもと専門家が契約書を作成して双方が確認、署名捺印する流れになります。
1-2-4.公正証書の作成
死後事務委任契約書は、元のままでも有効性に問題はありませんが「公正証書」にすることでトラブル防止になり、紛失の恐れも無くなります。公正証書作成のためには委任者・受任者の双方が公証役場に赴き、公正証書に署名捺印するのが原則です。ただし、やむを得ない理由がある場合は代理人を立てることもできます。
1-3.死後事務委任契約を結ぶことを検討すべき人
以下に該当する人であれば、死後事務委任契約のメリットを受けられるため、積極的に検討すべきです。
死後事務委任契約を結ぶことを検討すべき人
- 独身の人や子どものいない夫婦
- 家族や親族が高齢または遠方に住んでいて迷惑をかけたくない人
- 家族や親族はいるが死後にお世話になりたくないと考えている人
- 自分のエンディングについて強い希望がある人
- 内縁の夫婦や同性カップル
1-3-1.独身の人や子どものいない夫婦
死後事務委任契約を結ぶことにより、入院先や入居施設への負担を減らせます。入居施設などで亡くなった場合、最優先事項は親族・関係者への連絡です。しかし、身寄りや喪主になるべき人が不明だと、そもそも誰に連絡したらよいのかが分かりません。また、遺品を返す先がはっきりしない場合は、処分費用を入居施設が負担することになってしまいます。
1-3-2.家族や親族が高齢または遠方に住んでいて迷惑をかけたくない人
親族が高齢の場合は、通常の死後事務の履行が期待できないため、死後事務委任契約を検討します。また、高齢でなくても住居が遠方であり、わざわざ事務手続のために来てもらうことが心苦しい場合も同様です。
1-3-3.家族や親族はいるが死後にお世話になりたくないと考えている人
親族との関係が悪く、死後事務に関わって欲しくないと考えている人は、死後事務委任契約を検討すべきです。また、関係自体は悪くないものの「親族には触れて欲しくない内容」がある場合、希望する事務のみ委任契約する手段もあります。
1-3-4.自分のエンディングについて強い希望がある人
葬儀の内容や納骨先などに希望がある場合は、死後事務委任契約を結ぶことで実現する可能性が高まります。エンディングについての希望は、生前に親族の理解が得られない、または遺言では履行されない恐れがあるため、死後事務委任契約が有用です。
1-3-5.内縁の夫婦や同性カップル
法律婚に至っていない内縁の夫婦や同性カップルの場合は、法定相続人ではないため基本的に死後事務を行えません。しかし、死後事務委任契約を結んでおけばパートナーに死後事務を任せることができます。
2.専門業者や法律家に依頼する場合にかかる費用

死後事務委任契約は、依頼先や委任事項によってさまざまな費用がかかります。
死後事務委任契約にかかる費用
- 法律専門家に依頼した場合の契約書作成費用
- 公正証書作成手数料及び謄本作成手数料
- 履行する死後事務に応じた報酬
- 葬儀などの死後事務を行うための預託金
契約書作成費用や報酬は、法律専門家や業者が個別に設定できるため、信頼性などを見極めながら比較検討することも必要です。
2-1.契約手数料または契約書作成手数料
契約書は法律専門家に作成を依頼することになりますが、作成手数料は依頼先ごとに異なっており、数万円~30万円程度が相場です。
死後事務委任契約は口頭でも成立します。
しかし、契約してから履行(委任者の死亡)までに相当な期間があるため「内容があいまいになる、履行を担保するものがない」などの理由で、契約書を交わすのが現実的です。
2-2.公正証書作成手数料と謄本作成手数料
公正証書作成手数料と謄本の交付手数料は「公証人手数料令」により定められているため、下記の表を参考にしてください。
法律行為に関する証書作成の基本手数料
| 目的の価額 | 手数料 |
|---|---|
| 100万円以下 | 5000円 |
| 100万円を超え200万円以下 | 7000円 |
| 200万円を超え500万円以下 | 1万1000円 |
| 500万円を超え1000万円以下 | 1万7000円 |
| 1000万円を超え3000万円以下 | 2万3000円 |
| 3000万円を超え5000万円以下 | 2万9000円 |
| 5000万円を超え1億円以下 | 4万3000円 |
| 1億円を超え3億円以下 | 4万3000円に超過額5千万までごとに1万3000円を加算した額 |
| 3億円を超え10億円以下 | 9万5000円に超過額5千万までごとに1万1000円を加算した額 |
| 10億円を超える場合 | 24万9000円に超過額5千万までごとに8000円を加算した額 |
参考:Q. 法律行為に関する証書作成の基本手数料|日本公証人連合会
死後事務委任契約は、報酬額を目的の価額として手数料を算定します。
ただし、目的の価額を算定できないとして(無報酬の場合も同じ)目的の価額を500万円とみなして算定するケースもあるため、個別に公証役場に確認しましょう。
また、正本・謄本の交付手数料が1ページにつき250円かかります。
2-3.死後事務を依頼するための報酬
死後事務を依頼するための報酬に法的な定めはありません。たとえば、行政手続1件1万円~数万円、葬儀関係10万円~数十万円という具合に、委任先によって案件ごとに細かく設定されているのが一般的です。また、全ての死後事務を包括して、パック料金を採用している場合もあります。
死後事務を依頼するのが親族や友人であれば無報酬も考えられますが、法律専門家などに委任する場合は報酬が発生します。委任が広範囲に及ぶ場合、その分報酬額も多くなるため、契約する段階で慎重に検討すべきです。
2-4.葬儀など死後事務を行うための預託金
契約書作成費用や報酬とは別に、葬儀などの死後事務にかかる実費として数十万円~百数十万円程度を受任者に預けておくのが預託金です。委任者が死亡した場合、葬儀や納骨といった死後事務は早急に執り行う必要があります。
このとき、葬儀費用や経費を受任者が立て替えなくてもいいように、預けておいた預託金から充当していくことになります。
死後事務にかかる実費は正確に見積もることが難しく、多めに預けておき、精算後に残金を相続人に返還するのが一般的です。
2-4-1.預託金を預けずに実費を精算する方法
預託金を預けずに死後事務にかかる実費を精算する方法として、遺産から支払う、または保険により支払うパターンがあります。
遺産から支払う場合は、公正証書遺言書を作成して遺産の一部を費用として受任者に渡すことに。
契約時の出費を抑えられる一方で、遺言書作成手数料が別途必要です。
保険により支払う場合は、受任者を保険金の受取人とする生命保険契約を締結して、死亡時の保険金を経費に充てることになります。費用が月々の掛け金になるため、預託金よりも初期出費を抑えられますが、年齢や病歴によっては保険会社の審査にとおらない点がデメリットです。
3.委任する事務手続を減らすためにできること
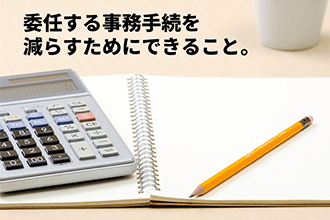
生前にできることは自ら済ませておき、委任する事務手続を減らすことで、トータルの出費を抑えられます。なぜなら、専門業者や法律家に依頼する場合、委任する事務手続が増えるほど支払う費用が高くなる依頼先が多いためです。
また、死後事務をスリム化することは、受任者の負担軽減になるため、結果的に死後事務が希望どおり履行されやすくなります。
3-1.事前に決めておけることは契約を済ませておく
葬儀の生前予約やペット信託など、生前にできる契約を済ませることにより、委任する死後事務を減らせます。
葬儀の手配や執行などは、死後事務委任契約の報酬のなかでも高額であり、受任者の負担も大きい死後事務です。葬儀の生前予約を行うことで、葬儀費用の目安が把握できたり、希望する葬儀の内容を明確にできたりといったメリットがあります。
ペットを飼っている場合はペット信託を利用して、あらかじめ引き取り先を決めておき、財産の一部を飼育費として信託しておくと安心です。
また、同居の親族がいる場合は相談して公共料金の名義を変更しておきます。
3-2.サービスやアカウントを定期的に見直して使わないものは解約する
今後使う予定のない「定額課金のサービスやSNSなどのアカウント」は、解約することをおすすめします。
クレジットカードから引き落とされるサービスは、利用者本人以外は明細を見ただけで何のサービスなのか把握しづらいことが多いため、解約までに時間がかかり無駄な出費につながります。
SNSのアカウントは利用していないものは削除して、残ったものについてだけIDとパスワードをエンディングノート( 自分の人生の終末について記したノート)に残しておくのがよいでしょう。
3-3.遺言書に死後事務についての希望を書いておく
「実現して欲しい死後事務ではあるものの、死後事務委任契約に盛り込む程度ではない事項」については、遺言書の付言事項として希望を書いておくこともできます。
たとえば葬儀や納骨などは、希望を遺言書の付言事項として書いておいたとしても、死後でないと相続人や受遺者に伝わりません。
そのため、準備が間に合わなかったり、事務が終わったあとに遺言書が開示されたりなど、現実的には希望を叶えられない可能性が高いです。
しかし、時間的に余裕がある、あるいは重要度の低い死後事務であれば、死後事務委任契約には盛り込まず遺言書の付言事項として書くことで、費用を抑えつつ実現する可能性を高められます。
4.死後事務委任契約を考えたときに知っておきたい3つの注意点
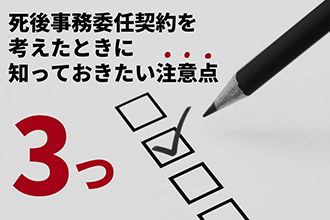
死後事務委任契約を検討するに当たって、以下の3つの点に注意することでスムーズに契約できます。
死後事務委任契約で知っておきたい3つの注意点
- そもそも契約できないケースがある
- 委任できない死後事務がある
- 相続人との間でトラブルになる可能性がある
4-1.認知症により意思能力がないとみなされると契約できない
認知症で意思能力を欠くと判断された場合は、契約が無効となります。
死後事務委任契約に限らず、契約の有効性を示すためには「当事者双方が意思能力を持っている」と、認められることが必要だからです。
意思能力の有無は一律に規定できるものではなく、ケースごとに判断されるものです。
契約締結の結果生じる基本的な権利・義務を理解する能力は、7歳~10歳程度の理解力が必要であるとされ、中程度の認知症の場合は意思能力を欠くと判断されます。
4-2.委任契約があっても履行できない死後事務がある
委任者の銀行口座の解約や不動産の処分は死後事務に該当しないため、委任契約に盛り込んでも履行できません。委任者の預貯金や不動産は相続財産であり、受任者が銀行の口座解約や不動産の処分を行うには、別途遺言書にて遺言執行者に指定してもらう必要があります。
4-3.相続人がいる場合は財産の処分や費用の支払でトラブルになる可能性がある
死後事務として遺品整理を委任され、その中に財産的価値のあるものが含まれている場合や、葬儀の規模や内容が相続人の意向と違っていた場合は、相続人との間でトラブルに発展することが考えられます。トラブルを未然に防ぐために、死後事務として委任する事項や範囲についてあらかじめ相続人に説明しておくことが大切です。お互いの認識のギャップを埋めておくことが重要なのです。
5.遺志を実現させるために死後事務の委任は信頼できる依頼先へ
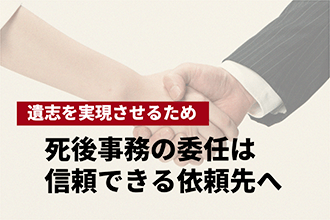
死後事務委任契約を結ぶにあたり、信頼できる依頼先を見つけることが重要です。
亡くなったのちの事務を委任できる範囲は広く、有効活用することで自分の思いを実現してもらえます。
日常生活や相続についての心配事があれば早い段階で相談し、かかりつけの弁護士(ホームロイヤー)を見つけておくことも安心につながるでしょう。
司法書士法人チェスターは、相続手続専門の司法書士法人という強みを活かして、死後事務委任契約の相談から事務の履行までを全面的にサポートします。遺志を実現させるための遺言書の作成や相続についての相談は、ぜひ一度司法書士法人チェスターにお問い合わせください。
今まで見たページ(最大5件)
関連性が高い記事
カテゴリから他の記事を探す
-
その他
















