- TOP
- はじめての相続 ~必要な知識と実務のすべて~
- 相続税における税務調査のすべて
- 〔相続税〕税務調査の選び方。嘘は課税の元。
〔相続税〕税務調査の選び方。嘘は課税の元。
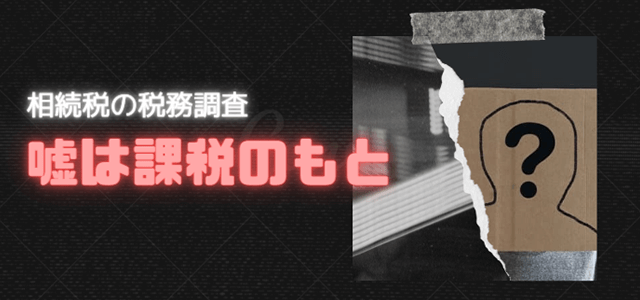
税務署が税務調査する先をどうやって選んでいるのでしょうか?
事前に税務調査をされない対策を立てるために、税務署の判断方法を学びましょう。
そもそも、税務署が税務調査を行う理由は大きく分けて2つです。
① 申告書の記載が間違っている
② 申告者が嘘をついている、または嘘をついている可能性がある
これらの間違いを正確に見つけるために、税務署は
1)機械で申告書をチェック(間違いを見つける)
2)独自の調査能力で申告内容の真偽を確かめる
これら2つの手順を踏みます。
つまり、間違いや嘘があった場合に税務調査を行います。
それでは一体、税務署は間違いや嘘をどのようにして見抜いているのでしょうか?
税務調査先の選定方法を詳しくご説明します。
1)まずは申告書の審査を機械でチェック
相続税申告書を税務署に提出した後、すぐに税務調査がくるわけではありません。まず申告書の計算が正しいかどうかを、システムで判断します。
申告書がセンター試験の解答用紙のように、機械に読み込ませる形式をとっている理由はここにあります。
【相続税の申告書】
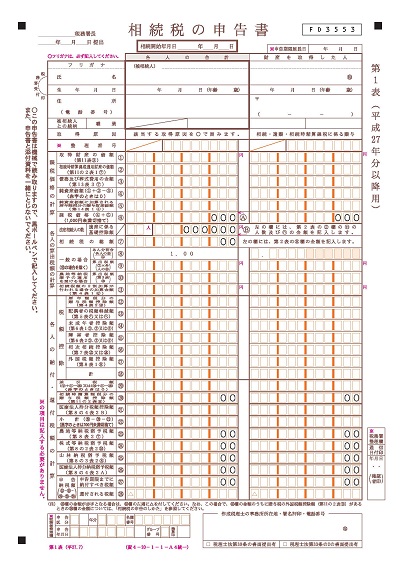
ここで、そもそもの相続税の計算が間違えていることが分かった時等は、すぐに税務署から連絡が入ります。
おおよそ、ご自身で申告されたかたは、この段階で税務署のチェックにかかる方が多いです。
この表面的な計算や記載方法等に誤りがなければ、次の審査段階へと移行します。
余談ですが、相続税の税務調査は申告書提出から早くてその年の秋頃~3年後程度まで長期間に及ぶ理由は、このようなステップを踏んで時間をかけて厳密な精査をするためです。
2)税務署の調査能力を侮るなかれ
よく相続人の方から
「申告しない財産があった場合、どうして税務署は分かるんですか?」
という質問を受けることがあります。
少し位、不動産や預金を申告しなくても分からないのではないかと、税務署を甘く見ていますと、あとで後悔します。
税務署は故人はもちろん、あなたの過去の納税記録や収入、登記情報など、必要な情報を全て持っています。
ではどのようにして税務署に分かってしまうのか詳細に解説しましょう。
土地や建物といった不動産
相続した不動産は、通常、相続人間での遺産分割協議後に、名義変更手続き(相続登記)を行います。
不動産の相続登記は、法務局で行いますが、その法務局で行った相続登記の情報が税務署も把握できるようになっています。
このため相続した不動産が、相続税申告から漏れていた場合には、税務署に分かってしまうのです。
また不動産収入がある場合には、所得税の確定申告で相続人へと引き継がれれば分かってしまうでしょう。
預貯金や株式等
預貯金や株式等については、税務署が相続人の了承を得ずに、銀行や証券会社に照会をかけることができます。
また相続開始時点の残高のみならず、過去に遡って、入出金や売買の履歴まで確認されるため、相続財産としての漏れはもちろんのこと、過去の生前贈与等も全て分かってしまいます。
生命保険
生命保険についても、生命保険会社に照会を行い、本人名義の生命保険のみならず、家族全員がどういった保険に加入しているのか、故人が保険料を負担したものはないか等、細かく調べられるため、税務署に分かってしまいます。
過年度確定申告書
ある程度の財産を築いた人であれば、所得税を多く税務署に納めているでしょう。
確定申告、源泉徴収に関わらず、税務署には過去の故人の所得データが蓄積されているため、そういったデータから推測される資産額よりも、相続税申告書への計上額が少ないと調査移行への大きな動機付けとなります。
中小企業オーナーであれば、法人決算書も
中小企業のオーナーであれば、毎年の法人税の確定申告書についても税務署にて確認できるため、そこから役員報酬の額や、法人への貸付金の有無等を細かく調べられてしまいます。
3)遺産総額3億円以上は要注意!?
上記のように、税務署では、相続財産として計上すべき財産の漏れの有無について、独自の調査を行っています。このため多くの事案では、相続税の税務調査開始の前から相続財産の漏れがある、もしくは漏れている可能性が高いということを税務署は掴んでいます。
また確定的な情報がない場合でも、形状漏れの可能性があれば、とりあえず税務調査に来るため、全国平均で相続税の税務調査率は約25%と高い数字になっています。
また財産総額が多ければ、特段の疑義がなくても、とりあえず税務調査に来る場合もあります。
日本全国の相続税申告の遺産総額の平均値が約2億5000万円ですので、財産が3億円以上あるようなケースでは、一般的に税務調査が来る確率が高くなります。
このように、税務署の調査能力や情報入手手段は多岐に渡り、実質的には財産を隠すことはほぼ不可能な状況となっています。
そうはいっても、無作為に調査先を選定しているわけではなく、多くのケースでは上記のような事前調査を入念に行い、財産の漏れがありそうな可能性のあるところを調査先に選定していますので、やはり当初の相続税申告書にどこまで税務調査に入られないような工夫や作成を行うかが重要となります。
4)税理士に依頼しなければ、税務調査が絶対くる!?
相続税申告書の第1表の右下に税理士の署名捺印欄があります。税理士に依頼しなければ、この申告書の表紙の税理士署名欄が空欄となりますので、税理士に依頼していないことが一目瞭然で判明します。
そうすると税務署は、「税理士に依頼していないんだったら、何か間違えているかもしれない」ということで、税務調査に選定する確率が大幅に高まります。また税務調査が来た後も、税理士がいないため、納税者に不利な提案や指摘を行う可能性もあります。
動画にて相続税の税務調査で聞かれやすい質問も公開中です。
まとめ
税務署は申告書の間違いや嘘を見つけるために血眼になってチェックし、何かあれば税務調査を行います。
いわゆる完璧な申告書を提出すればまったく問題がなく、新しく税金支払うのかとドキドキする必要もなくなります。
こういったことを考慮すると、相続税申告は相続を専門に勉強をしている税理士に依頼することが一番ミスと心配がなく、賢明かもしれません。
相続税専門のチェスターなら税務調査の立会いもお任せください
税務調査の対象となってしまった方はまずは慌てず、相続税のプロフェッショナルにご相談ください。
税理士法人チェスターの税務調査立会いでは元税務署長の者がしっかりと対応させて頂きます。
詳しくはこちらをご覧ください。
税務調査に関するサービスページはこちら››
相続税における税務調査のすべて
- 自分で相続税の申告を行った
- 相続が専門でない税理士に相続税の申告を依頼した
上記2つに当てはまる方は税務調査を行われる確率が極めて高いです。
なぜ税務調査を受けることになるのか?当日、何を聞かれるのか?追加で課税されることはあるのか?
税務調査前にやるべき準備から当日の受け答え、さらには後日の対応まで税務調査を難なくこなすための方法を弊社の実務から得た経験からご紹介します。
相続税の税務調査対策を見る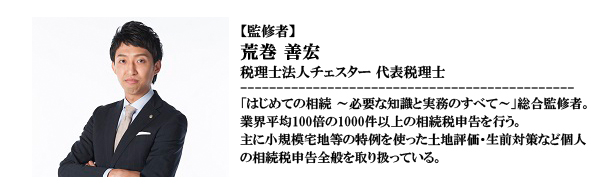
お約束いたします
チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。









