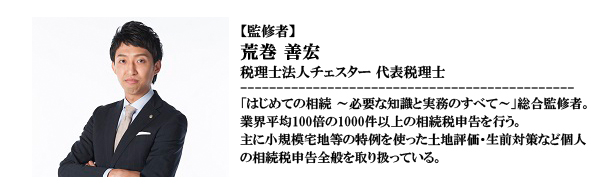- TOP
- はじめての相続 ~必要な知識と実務のすべて~
- 相続税における税務調査のすべて
- 相続税の税務調査の確率は10%!10人に1人が相続税申告後に国税庁からチェックされています。
相続税の税務調査の確率は10%!10人に1人が相続税申告後に国税庁からチェックされています。
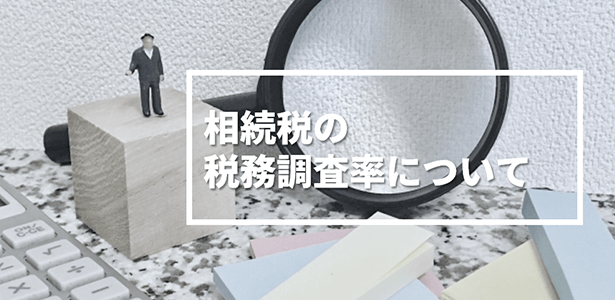
相続税申告書を提出した人にとって、新たに相続税の支払いを課される税務調査は怖い・入られたくない存在だと思います。
では、実際にあなたの元に税務調査が来る可能性はあるのか?
国税庁が発表している統計データを元に、相続税の税務調査が行われる確率を割り出し、検証していきます。
1.相続税の申告をした人のうち、10人に1人が税務調査をされている
国税庁が発表している統計データを見ると、平成29年事務年度において、税務調査の件数は12,576件です。
これに対して、年間の相続税申告件数が平成28年事務年度で136,891件ですので、税務調査の割合を求めると約10%のご家庭に相続税の税務調査が来る計算となります。
つまり、相続税の申告をした10人に1人が、税務調査を受けています。
中には虚偽の記載をする方もいますが、単純に財産の試算や相続税の計算を間違えて税務調査を受ける方も多いです。
また、10年間、相続税の申告をやるなかでわかったのが、税務調査を受ける方は
・ご自身で相続税の申告をされた
・相続税の申告が必要なのに、申告しなかった(申告漏れ)
・相続税を専門としていない税理士に頼んだ
といった方が多いように見えます。
*国税庁の統計データ。相続税の申告件数・調査件数などが掲載されています。
(平成28事務年度における相続税の調査の状況について)
2.贈与税はズバリ100人に1人が調査されている
上記では、相続税の調査率をご紹介しましたが、では贈与税も税務調査の対象となるのでしょうか?
結論から言うと、贈与税も税務調査の対象となります。
贈与税の税務調査の確率ですが、贈与税の年間調査件数が約4,000件前後、贈与税申告者が年間約40万人います。
この数字から、調査率は僅か1%程度、100人に1人が税務調査を受けている計算となります。
このように見ますと、相続税の調査率がいかに高いかがお分かり頂けるかと思います。
3.税務署の職員さんに聞いてみた。税制改正後、税務調査の件数は増やすのか?
平成27年に相続税が改正され、基礎控除が引き下げられたことで、相続税申告件数が2倍近くになるという予測がされておりましたが、令和元年現在、調査率は10%です。
もし当時の予測である調査率20%を維持したとして、年間で約24,000件もの税務調査が行われる想定になるわけですが、
果たして、この膨大な件数を税務署はこなすことができたのでしょうか?
直接、税務署の職員さんにヒアリングしたところ
「相続税が改正されたからといって、相続税部門(資産課税部門)の税務署の職員数が増えているわけではなく、物理的な調査件数を増やすことは難しい」
という回答でした。
つまり相続税の申告件数は増えるけれど、それを処理する税務署の職員の人数は増えないので、相続税の調査率は改正前と比べてかなり低くなるということになります。
ただし、これを見て「税務署が手が回っていないようだから、ちょっとぐらいミスしても大丈夫だろう」と考えて相続税の申告をするのは危険です。
相続税の申告数が多くとも、税務署は必ずあなたの申告書をチェックします。
それが例え、数年経っていてもです。
そして、税務署が申告書のチェックをした際に、例えば税金の計算を間違っていた場合、その間違った分の税額を追加で払えばよいという甘いものではありません。
たとえ、悪意がなかったとしても、過少申告加算税というペナルティが本来払うべき税額に加えて追加で15%かかります。さらに、その間違いに悪意があると認定された場合には、最大で40%ものペナルティが追加でかかる可能性もあります。
4.相続税専門の税理士法人チェスターは税務調査率が僅か1%
相続税の税務調査率は全国平均で約10%となっていますが、相続税専門の税理士法人チェスターでは、様々な税務調査回避の工夫やノウハウによって、僅か1%程度にまで税務調査率を引き下げています。

弊社のお客様で税務調査をすることになった2件の実例をご紹介します。
これらは、一般的な税務調査のよくあるケースにもなります。
(1)遺産総額が大きい(3億円以上)
遺産総額が3億円以上のお客様の申告を行った後、税務調査が行われました。
調査が行われた理由は、申告書に不備があったわけではなく、遺産総額が大きいためでした。
税務署としては疑わしい部分が特段なくとも税務調査を積極的に行う傾向にあります。
遺産総額が大きいとそれだけ申告書を作成する際のミスも起きやすく、さらに税率も大きくなるので、ミスがあれば、追加でとれる税額が大きくなるからといったことも関係しております。
この時は、申告書の記載も抜けがなかったので、調査官から電話がきた1週間後に、申告書のチェックと軽い雑談をして終わった程度でした。
また別の場合ですと、申告書がミスしていることを前提にお話をされる調査官もいらっしゃいました。
そういった方はお話というよりも、申告書のミスを発見し相続人に認めさせることを目的にしておりますので、こちらも相応の対応をいたしました。
どのような調査官が来られるかは当日になるまでわかりませんので、事前の準備が税務調査をスムーズに進めるために大事なこととなります。
(2)被相続人の生前の預金から多額の不明出金がある
被相続人となる親が自分で管理している預金から、亡くなる直前に200万円の出金をされていた場合、税務調査を行われることは多いです。
なぜならば、税務署はその200万円をどこかに隠しているのでは?と疑うためです。
弊社に来られたお客様で、このような不明出金があった方は実際に税務調査を行われましたが、申告前にすでに調査済み。
事前に税務調査をされることがわかっていたので、お客様にその旨をお伝えしたうえで申告をしました。
税務調査当日もお客様と弊社による打ち合わせのもと行ったので、スムーズに申告内容の確認だけで済み、追徴課税も申告書の再提出もなく税務調査を終えました。
まとめ
単純な数字を見ると、相続税の申告をされた方の10人に1人と高い確率で税務調査を受けることになります。
さらに掘り下げて、どういった人が税務調査の対象になるのか?
対象者の選定方法はどのようにして行われるのか?
そしてあなたが税務調査を受けないためにどうしたらいいのか?
といった疑問がでてくると思います。
これらのお話は、次回の「相続税の税務調査の選定方法」について解説したいと思います。
相続税における税務調査のすべて
- 自分で相続税の申告を行った
- 相続が専門でない税理士に相続税の申告を依頼した
上記2つに当てはまる方は税務調査を行われる確率が極めて高いです。
なぜ税務調査を受けることになるのか?当日、何を聞かれるのか?追加で課税されることはあるのか?
税務調査前にやるべき準備から当日の受け答え、さらには後日の対応まで税務調査を難なくこなすための方法を弊社の実務から得た経験からご紹介します。
相続税の税務調査対策を見る