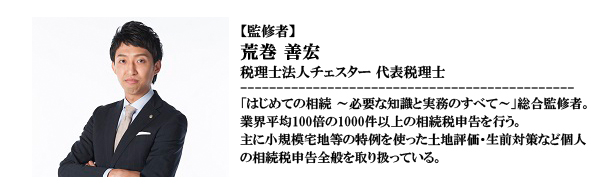- TOP
- はじめての相続 ~必要な知識と実務のすべて~
- 相続税の債務控除すべて
- 相続税の債務控除の対象になる債務・ならない債務
相続税の債務控除の対象になる債務・ならない債務

相続税は、亡くなった人の財産に一定の税率を乗じて相続税額を計算します。
この財産の中には、土地、建物、現預金、有価証券などのプラスの財産だけでなく、亡くなった人に借入金や未払金などの負債があった場合には、その負債を財産からマイナスできるのです。
この財産から負債をマイナスすることを、相続税では「債務控除」といいます。
この債務控除は財産を圧縮することが可能なので大きければ大きいほど相続税の節税につながります。
1)債務控除とは?
債務控除の対象となる債務は、相続税法で下記のように書かれています。
「亡くなった人の債務で、亡くなった際、現に存在するもので、確実と認められるもの」
若干、ややこしい書き方ですが、亡くなった人の負債で亡くなったあとに支払うことが確定しているものは財産からマイナス出来ますということです。
2)債務控除の対象となる債務
債務控除の対象となる債務は具体的には下記のようなものになります。
・銀行などの金融機関からの借入金
・その他個人などからの借入金
・亡くなった後に支払う所得税、住民税、固定資産税などの公租公課
・病院に対する未払医療費
・水光熱費、電話代などの公共料金等の未払金(亡くなった人が使用していた期間に限る)
・賃貸不動産のテナントから預かっている敷金
・買掛金などの事業上の未払金
3)債務控除の対象とならない債務
債務控除の対象とならない債務は具体的には下記のようなものになります。
・団体信用生命保険(通称、団信)で補填される住宅ローン
・墓地や仏壇などの非課税財産(相続税がかからない財産)に係る未払金
・保証債務
・亡くなった後に発生する下記のような費用
相続財産の名義変更費用(登録免許税、司法書士報酬など)
相続税申告にかかる税理士報酬
遺産分割交渉等に係る弁護士報酬
戸籍謄本など身分関係書類を取得するための諸費用
信託銀行などに支払う遺言執行報酬
相続税の債務控除すべて
債務控除に関する情報を無料で公開中。
亡くなった方自身の借金等だけでなく『葬式費用』も債務控除に含まれ、うまく使えば節税効果も見込める控除です。
しかし、債務控除の一番の問題は「何が」葬式費用に該当するのかの判断。
例えば、墓石は葬式費用にならないが、戒名料は葬式費用に該当するなど。知識がなければ必要のない税金を支払ったり、申告ミスとして税務調査を受ける元になります。
債務控除を賢く使うために「相続税の債務控除のすべて」を見ると
- あなたは葬式費用でどこまで節税できるのか
- 債務控除を使うために書くべき申告書
- 葬式費用を債務控除に適用するために賢く使う具体的ノウハウ
これらすべての知識が身に付きます。
相続税の払い過ぎにならないように、今すぐに債務控除のすべてを確認してください。
債務控除を使って相続税を節税する